当法律事務所では、初回無料の法律相談を実施しております。弁護士に相談をするという事に不安を感じている方や、これぐらいの悩みを相談していいのだろうか、というお気持ちを持たれる方など様々なご事情の方がいらっしゃいます。そこで無料相談でお話を伺い、相談者様が安心して頂けるよう、ベストな選択を一緒に考えております。
また弁護士に早めにご相談いただく事で、問題が整理され解決策が見いだせたり、実際に弁護士と話しをする事で雰囲気や相性など確かめて頂けるかと思います。まずはお気軽にご相談ください。
お知らせ
- 25.11.17休業案内
-
年末年始休業のお知らせ
- 24.11.28重要
-
愛知総合法律事務所 電話番号変更のお知らせ
- 25.12.11採用情報
-
ウィンタークラーク募集のお知らせ(79期司法修習生・80期司法修習予定者向け)
- 25.11.25ご案内
-
79期司法修習生対象 事務所訪問・WEB面接のお知らせ
- 25.11.18ご案内
-
79期司法修習生対象 WEB説明会のお知らせ
- 25.10.22ご案内
-
(終了しました)ホームページメンテナンス実施のお知らせ
- 25.08.22重要
-
【ご注意】弊所名を無断使用した不審な連絡・表示について
初回無料の相談
面談、オンライン、電話による法律相談を実施しています。
どの相談方式でも初回のご相談は無料です。
面談、オンライン、電話による
法律相談を実施しています。
どの相談方式でも初回のご相談は無料です。
- ※ご相談内容によっては法律相談に応じられないことがありますので、予めご了承ください。
- ※面談でのご相談の場合、初回(30分程度)無料です。
- ※ご相談前にお聞きします個人情報は、相談受付のために必要な聞き取りになります。
個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。
選ばれる理由
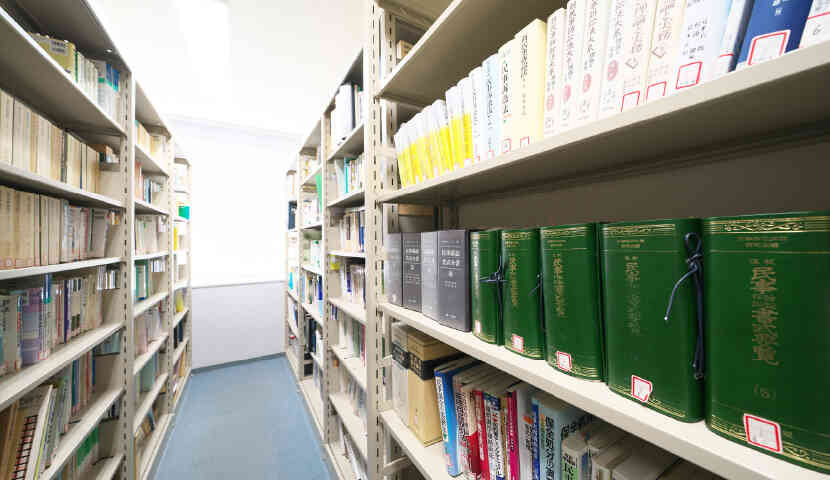
専門部が充実
名古屋丸の内事務所では、事件の種類ごとに分かれた【離婚部】【相続部】【破産・管財部】【医療法務部】【労働部】があり、専門のチームが事件解決に向け動いています。

初回の相談料は無料
少しでも気軽にご利用いただけるよう、お電話や面談、オンラインによる無料法律相談を実施しております。丸の内本部事務所では、土日の法律相談も承っております。

ワンストップ体制
名古屋丸の内本部事務所では、弁護士の他に、税理士、司法書士、社会保険労務士が複数在籍しており、弁護士と共同で事件解決に向け活躍しております。
法律事務所をお探しの方へ
愛知総合法律事務所は、中部・東海圏でも最大規模の法律事務所として弁護士が多数在籍しております。(男性弁護士・女性弁護士ともに在籍)。法律事務所といえば、弁護士1名~数名の個人事務所というイメージを持たれる方も多いと思いますが、弁護士が多数在籍している事は、ご相談者様にとって大きなメリットがあります。
当事務所は2024年は年間で10000件以上のお問合せをいただきました。(2024年1月~12月、全事務所のお問合せ数合計)
ご相談内容は1人1人、状況や思いも違っており、まったく同じお悩みはありません。弁護士1人1人がご相談に真摯に向き合い、得たノウハウを事務所全体で共有することにより、事件解決の道筋を立てる精度や専門性を高め、安定したリーガルサービスの提供に努めております。
また、当事務所には弁護士数に応じ、事務スタッフも多く在籍しております。これによって、複数人体制や事件分野ごとに専門チームが組織出来るという点は、大きい事務所の強みであり、質の高いリーガルサービスに繋がっているというメリットでもあると思います。
弁護士を探される上で、事務所の規模や場所を参考にされる方もいらっしゃると思います。当事務所は名古屋市内に3つの事務所がございますので、ご利用しやすい事務所にてご相談いただくことが可能です。
新瑞橋事務所(瑞穂区)

名古屋新瑞橋事務所は、地下鉄新瑞橋駅より徒歩すぐに立地しております。瑞穂区、南区、緑区、熱田区、港区、昭和区、天白区をはじめとした近隣の方々にお気軽にご相談頂ければと思います。
藤が丘事務所(名東区)

名古屋藤が丘事務所は、地下鉄東山線・リニモ「藤が丘駅」徒歩1分の場所に立地しており、名古屋市名東区、守山区、長久手市、尾張旭市、瀬戸市方面から交通機関を利用してもアクセスしやすい場所にあります。
法律相談について
人生の中で法律事務所に相談をするという事は、あまりない事と思います。ネットなどで名古屋の弁護士と探しても、実際にどのように相談したらいいのか、
何を話したらいいのか、不安になる事もあると思います。当法律事務所の弁護士へ相談される際の流れについて、ご説明いたします。
1 お電話・メールフォームにてお問合せください
初めて法律相談をされる方は、お電話でのお問合せがおすすめです。 こちらでは、ご予約をおとりするために、事務員が対応いたします。 お電話をいただいた方の氏名・ご住所・お電話番号、相手方の氏名等必要情報の聞き取り、ご相談内容の要旨を確認し、ご予約をお取りいたします。 まずは、050-1780-5321までお電話ください。メールフォームでのお申込みをご希望される方は、こちらからお問合せください。
2 無料相談の方法
当法律事務所ではご相談者様の状況に応じた3つの無料相談(面談相談・電話相談・オンライン相談)があります。弁護士への法律相談が初めての方は面談による相談がおすすめです。詳細はこちら
3 弁護士への無料相談
法律相談の際には、ご相談内容に関連する資料(証拠)などのご準備がありますと、弁護士としてもその後の見通しをたてやすくスムーズになります。 ご相談者様の抱える問題について、不安な事やわからない事、弁護士費用なども、遠慮なくご質問ください。 また、無料相談はその後必ず依頼しなければならないものではありませんのでご安心ください。
どこまでが無料相談の範囲か
無料相談は、初回30分程度を無料としております。ただし、離婚・相続の面談相談は初回60分無料です。お受けできる内容の範囲は、相談方法によって異なるためこちらからご確認をお願いいたします。
土日・夜間の無料相談
名古屋丸の内本部事務所では、平日の日中お忙しい方に向けて土日・夜間の法律相談を実施しています。 ご希望の方は、まずはお電話いただき、受付の案内に沿ってご予約を頂ければと思います。 法律問題でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
ご依頼の場合の弁護士費用について
正式にご依頼頂く場合の弁護士費用に関しては、具体的な内容によって変わりますので、詳しくはこちらをご参照ください。 また初回無料の相談の際には弁護士から費用についてもご説明しますので、ご不安に思う事や気になることなど遠慮なくご質問頂ければ幸いです。
弁護士に相談するタイミングについて
弁護士にいつ相談するのがよいか、というと「早ければ早いほど」良いという事となります。法律相談において、とにかく早く相談するほど、メリットが多いためです。
早く相談するメリット
法律相談において、早くご相談頂くことによって、弁護士側からご提案できる選択肢が増え結果的にトラブルが解決しやすい傾向にあります。 例えば、時間が経過すると証拠が失われたり、記憶が曖昧になる事があります。また、時効、借金問題、家庭内のDVなどの問題は時間が経つほど問題が悪化する傾向にあります。 そのため早めに弁護士までご相談頂く事でトラブル解決へと導きやすくなります。
安心感を提供できる早くご相談頂く事で、当然対処方法も早く知る事ができます。例えば、離婚や遺産相続など感情的な衝突が多い問題の場合、弁護士が間に入るだけでも味方が出来て安心して頂ける事もあると思います。 一人で抱えていた悩みから解放されて、精神的に安心できるというのは大きなメリットではないかと思います。
早めの相談は、慰謝料請求されたとか弁護士や裁判所から通知が来た場合などの緊急性があるケースだけでなく、特に深刻ではないと思われる問題でも 弁護士が判断すると早く手を打つ必要のある問題という事があります。病気の早期発見のようなイメージです。
そのためにも、是非初回無料の法律相談をご利用ください。 「こんな相談していいのかな」と思われるようなご相談でも大丈夫です。 深刻な問題でなくとも、将来を見据えて弁護士が予防策や回避策などの提案をする事ができますので、漠然とした不安から解放されてご安心頂けると思います。 まずは初回無料の法律相談までお問合せください。
法律相談は愛知総合法律事務所
弁護士法人愛知総合法律事務所は、40年以上にわたり愛知県名古屋市を中心に活動し、現在中部・東海圏で最大規模の法律事務所として多数の弁護士が在籍しています。
また、税理士、司法書士、社会保険労務士も在籍しているため、様々な法律問題をワンストップで対応する事が可能です。
「大きい事務所だから敷居が高い」「こんな事を相談して良いのだろうか」と感じられるかもしれませんが、心配はご無用です。
私たちは街の法律専門家として、親身になって問題解決に向けて一緒に取り組みます。
病気になった時に病院に行かれるように、法律問題で困った時は弁護士にご相談下さい。
総合法律事務所として
当事務所は、総合法律事務所として幅広い分野の法律問題に対応しております。 離婚問題や相続問題、交通事故、借金問題などの民事と呼ばれる分野だけでなく、 刑事事件の弁護活動、法人向けの企業法務や会社設立、法人トラブルに関わる事など多岐にわたる法律分野をカバーしております。
また、弁護士だけでなく、法律事務もスキルアップに力を入れ、法律セミナーを受講するなど日々研鑽を積んでおります。 敷居は低く、専門性の高いリーガルサービスをご提供しますので、安心して頂ければと思います。 名古屋で弁護士をお探しの方は、愛知総合法律事務所まで是非ご相談ください。
名古屋で多くの方に選ばれ続けている、弁護士法人愛知総合法律事務所が全力でサポートをして、最善を尽くします。
Blog -ブログ-
-
労災認定されなかったらどうする?対処法を社労士が解説
労災における「不支給決定通知書」の要点とその後 今回は申請した病気やケガが労災ではない(労災不認定)と判断された場合の「その後」についてお話します。不支給決定通知書のチェックポイント 労働基準監督署の不支給(不認定)の決定通知書には不支給の理由が簡単に記載されています。記載内容を読んでも理由がよくわからない場合は、提出先の労働基準監督署に詳細を確認しましょう。それでもなお決定に納得がいかない場合は「審査請求」を行うことができます。審査請求には厳格な申請期限がありますので、その点注意しましょう。労災不認定された後の選択肢 申請した病気やケガが労災でないと判明した場合、その後は①決定を受け入れ、健康保険給付へ切り替えを行う ②不服申し立て(審査請求や再審査請求)を行うなどの選択肢が考えられます。① 不支給の決定を受け入れ、健康保険へ切り替える 健康保険にも、病気やケガで働けず、給与を受けられない期間中の生活を支える『傷病手当金』の制度があります。自分が支給対象となるか、具体的な手続き方法についてはご自身が加入している健康保険協会や健康保険組合に問い合わせを行い確認しましょう。なお傷病手当金を受ける権利は「労務不能の日ごとにその翌日から2年」で時効になります。労災ではないことが確定したら、傷病手当金の手続きは早めに行いましょう。 また労災でないと確定した場合は、医療費も当然に健康保険を利用することができます。これまでの医療費は以下の手順で切り替え手続きを進めます。イ) これまで「労災かも」として自己負担0円で受診していた場合 受診した医療機関や薬局に「労災ではなかった」と伝えましょう。一般的には病院側で健康保険に切り替えを行い、本人へは本来負担すべき3割分の医療費が請求されます。具体的な支払い方法などは医療機関の指示に従って進めます。ロ) これまで医療費全額(10割)を自分で立て替えていた場合 本来、健康保険から受けられる7割分の返金を受けることができます。10割負担した医療機関の領収書(原本)と療養費支給申請書の2つを加入健康保険協会等に提出し手続きを進めるのが一般的ですが、念のため加入中の健康保険協会等に相談のうえ、手続きを行うのが安心です。② 不服申し立て 先に記載の通り、労働基準監督署の労災不支給決定に納得できない場合、その決定の取り消しや変更の申し立てを行うことができます。この手続きを「審査請求」といいます。審査請求は「納得できません!」と主張するだけでは足りず、一度出た決定を覆すには、客観的な証明が必要とされます。審査請求を検討する場合は、誰もが納得しうる証拠や資料を揃えることができるかを検討しましょう。◎ステップ (1) 厚生労働省HPや労働基準監督署で「審査請求書」の書類入手 (2) 審査請求書類の記入(*) (3) 都道府県労働局へ審査請求書を提出(持参/郵送いずれも可) (4) 審査請求書受理・担当の労働者災害補償保険審査官決定 (5) 審査開始 (6) 決定(認容/棄却) (*)「審査請求の理由」は具体的に記載しましょう。また労災不認定に至る経緯を確認(保有個人情報開示請求を行い内容を確認)したうえで、「詳細は追って主張」という手順で進めるのが効果的です。 ◎審査請求制度の概要 イ) 請求権者:被災労働者やその遺族 ロ) 請求先 :労働基準監督署の所在地を管轄する都道府県労働局 ハ) 請求期間:決定があったことを知った日の翌日から3か月以内 ニ) 費用 :無料不服がある場合その2 再審査請求(第2段階) 労働者災害補償保険審査官の審査請求の棄却に納得できない場合は、労働保険審査会に対して決定の取り消しを行うことができます。この手続きを「再審査請求」といいます。所定の様式に再審査請求の趣旨・理由等を記載したうえで、審査請求の決定書が送付された日の翌日から2か月以内に、東京都港区の労働保険審査会へ書類を提出し、手続きを進めます。また追加の証拠書類等の提出も可能です。審査請求同様、結果を覆すためには客観的な証明を求められます。 なお審査請求、再審査請求はどちらも不支給決定が取り消される確率が非常に低い、厳格な手続きです。手続き検討の際は弁護士や社会保険労務士などの専門家の意見を聴くことをお勧めします。訴訟(第3段階) 再審査請求の裁決に不服がある場合や一定期間を経過しても決定がない場合は原処分の取消訴訟を行うことができます。なお労災の原処分の取り消し訴訟は提訴期間に厳格なルールがありますので、手続きを進めたい場合はお早めに弁護士にご相談ください。 なお当事務所では社会保険労務士が行った労災手続きを、ワンストップで弁護士につなげることができ、取り消し訴訟のための準備もスムーズに進めることが可能です。ケース別・証拠収集と主張 長時間労働による精神疾患 長時間労働による精神疾患を労災として認めてもらうためには、なにより残業時間の証明が重要です。会社には従業員の労働時間を管理する義務があるため、タイムカードは当然備えられているものの、その情報を開示してもらえないことやそもそもタイムカードがない会社もいまだに多くあります。 このような場合でも、「会社からのメールの送信時間」や「家族宛てのLINEの送信履歴」「勤務時間を記録した日記」なども参考になる場合がありますので、勤務していたことを証明できそうな資料を一度集めてみましょう。基礎疾患の悪化(腰痛、心疾患など) 労災の認定には「業務起因性」と「業務遂行性」が必要ですが、基礎疾患の悪化の場合、これらに加え「業務の過重負荷」が重要な判断要素となります。例えば脳や心疾患、腰痛の場合の業務の過重負荷の判断基準は以下の通りです。 (例)脳・心疾患の場合:「自然経過を超えて基礎疾患を著しく増悪させうることが客観的に認められる」負荷があったか? (例)腰痛の場合:一般的に腰痛は加齢に伴い骨の変化によって発症することが多いが、その変化が「通常の加齢による骨の変化の程度を明らかに超える」負荷があったか? もともと自分が持っていた病気が業務によって悪化したことを証明するのは、大変難しいことですが、主治医や弁護士、社会保険労務士等の専門家の意見を聴きながら、医学的な根拠や過重負荷について今一度検討してみましょう。よくあるご質問(FAQ) Q. 申請から決定まで、どれくらいの期間がかかりますか? A. 労災の審査は3か月~長い場合は1年程かかることもあります。精神疾患や過労死等の審査には長い時間がかかる傾向です。また審査請求や再審査請求も標準的な審査期間はありませんが、事案の重大さや複雑さによって大きく異なり、審査が長期化することも多い印象です。Q. 審査請求の期限を過ぎたら、もう何もできませんか? A. 原則請求期限内でなければなりません。ただし次の事情がある場合は疎明資料を提出することで手続きを認められることがありますので、行政機関に問い合わせを行ってみるのが良いでしょう。 ・天変地変など一般に請求人が如何ともすることができない客観的事情がある場合 ・請求人は期限内にできる限りの努力をしたものの、審査請求の意思を行政に表明することが困難なほどの事情(病気等)があった場合 (参考:労働保険審査請求事務取扱手引)Q. 会社が非協力的で、労災申請に必要な書類が集まりません。どうすればよいですか? A. 申請書類のすべての内容が記載されておらず、分かる範囲のみ記載をしていたとしても、事情を具体的に説明することで労働基準監督署に書類を受け付けてもらえる場合があります。まずは管轄の労働基準監督署もしくは弁護士、社会保険労務士などの専門家へ相談をしてみましょう。Q. 労災で休んだ後、復職する際のコツはありますか? A.まずは本当に復職可能かを主治医とよく相談しましょう。その上で、会社とは「復職の時期」・「復帰後の業務内容や勤務時間」・「業務での配慮事項」など、お互いが納得できるよう話し合いを行います。完全復帰に自信が持てない場合は、リハビリ出勤の期間を設けるなど、復職を目指し段階的な出勤が可能かを会社に相談してみるのも良いと思います。
-
65歳までの雇用義務化に対応する就業規則変更チェックリスト
なぜ今、就業規則の見直しが急務なのか?高年齢者雇用安定法改正のポイント 65歳までの雇用義務化とは?企業が必ず対応すべきポイント 平成18年4月1日に改正施行された高年齢者雇用安定法により、企業には65歳までの雇用確保措置導入(平成18年4月1日時点では62歳、平成25年4月1日までに段階的に65歳まで引き上げ)が義務化され、この雇用確保措置は、以下のいずれかにより講ずることとされました。① 定年の引き上げ ② 継続雇用制度の導入 ③ 定年の定めの廃止この内、②については、対象者の基準を定める労使協定(以下、「継続雇用協定」という)の締結が可能が可能とされていたため、本人が継続雇用を希望しても、継続雇用協定に定める基準に該当しなければ、65歳まで継続雇用する義務はありませんでした。 平成25年4月1日に改正施行された同法では、この継続雇用協定を廃止することとなりましたが、経過措置として、平成37年(令和7年)3月31日までの間は、一定の方(厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢以上の方)を対象に、引き続き継続雇用協定を使用することが可能とされていました。 そして、令和7年4月1日にこの経過措置期間が経過し、全ての企業において、希望者全員を65歳まで雇用することが義務となりました。 これに伴い、これまで上記経過措置を利用されていた企業では、就業規則の改正が必要となります。 なお、経過措置を利用されていた企業でも、段階的に雇用義務年齢が引き上げられているため、既に雇用延長に向けた取り組みを実施されているものと思いますが、対応が後手となっている企業の方は、給与等コスト、若手のポスト確保、退職金の精算等、重要事項についてトラブルとなる可能性がありますので、直ぐに対応が必要です。対応が遅れるとどうなる?就業規則の不備が招く労務トラブル事例 雇用延長に伴い整備すべき事項として、以下が挙げられます。 ① 給与額 ② ポスト③ 勤務体系④ 退職金の精算時期・計算期間 上記の対応等について整備されないまま、「今まで通りでいいか」や「定年しているから、給与は〇%カットでいいでしょ」と安易に対応すると、人件費の増大や未払賃金が発生するリスク等があります。継続雇用・定年延長のメリット・デメリット比較 「定年引き上げ」と「継続雇用制度」、どちらを選ぶべきか 65歳までの雇用延長方法が3つあることを冒頭で述べさせていただきました。多くの企業では、この内、「定年引き上げ」と「継続雇用制度」の選択で悩まれるかと思います。 「定年引き上げ」については、就業規則等による特約が無い限り、従前の雇用契約がそのまま継続されることになりますので、安定した雇用に繋がりやすくなります。 「継続雇用制度」については、多くの場合、60歳等の定年年齢でこれまでの雇用契約を終了させ、再度新たな契約を締結する制度を指しますので、この場合、定年という節目に今後の勤務について考えるきっかけとなり、その結果、退職へ繋がるリスクがあります。しかし、年齢を重ねると、これまで通り勤務することが体力等の面から難しい方もみえますし、従前通りの給与額やポストを維持することが、人件費の増大や次世代の昇進機会を奪うというリスクに繋がることが考えられますので、そのような心配のある企業については、定年後に新たな雇用契約を結ぶ継続雇用制度の導入が良いかもしれません。各制度の導入ステップと、企業が陥りがちな失敗パターン 1. 導入ステップ ① 65歳までの雇用確保措置の選択 社内の実情を踏まえたうえで、3つの制度のうち、どの雇用確保措置を取り入れるか選択します。 ② 雇用延長後の雇用条件決定方法のルール化 定年延長後の雇用条件を変更する場合は、この変更ルールを定める必要があります。 一言で「雇用条件」としておりますが、この中には、給与、勤務時間(勤務日)、ポスト、業務内容等、あらゆる項目が含まれます。 これらにつき、いつ、どのような基準で、どのように決定するかルール化する必要があります。 ③ 退職金精算時期の決定 精算時期を従前の定年年齢にするのか、雇用延長が終了した時にするのか、雇用延長が終了した時とするのであれば、計算期間も延長するのか等、決定する必要があります。 ④ 決定したルールを就業規則へ盛り込む これら決定したルールの多くが労基法上において就業規則へ記載すべき内容とされていること、また重要な労働条件であり従業員の方との間でトラブルとなる可能性が高いため、予め就業規則へ明記する必要があります。選択を誤らないために。制度設計で社労士が果たす役割 勤務延長後の雇用条件決定については、いわゆる同一労働同一賃金の規制も絡むため、安易に制度設計を行うと、未払い賃金請求等のリスクが発生します。しかし、従前条件継続では、コストの増大や若手の昇進機会喪失等、様々な組織体制の歪みを生じさせる可能性があります。 安易な決定は避け、顧問社労士等へ相談のうえ、各企業の実情を踏まえた制度設計を行うことをお勧めします。【最重要】トラブルを未然に防ぐ!賃金・労働条件の見直し方 年再雇用後の賃金はいくらが妥当?「同一労働同一賃金」との関係性 定年再雇用後の賃金を、「定年前の●%」や「●円減額」のように一律に定めている場合、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)に定める、同一労働同一賃金の規定に違反する可能性があります。 同一労働同一賃金では、フルタイムかつ無期雇用者(いわゆる正社員)と、短時間または有期雇用者(短時間・有期雇用者)との間で、不合理な待遇差を設けることを禁止しています。定年後再雇用者の方は、労働時間を短縮することや、契約期間を設けて勤務継続することが多いため、その場合、この規制の対象となります。 待遇差がある場合、正社員と短時間・有期雇用者との間の、職務内容、職務内容及び配置の変更の範囲の差に応じたものでなければ、不合理な待遇差と判断されることになります。また、不合理な待遇差であるか否かは、各待遇の性質および付与目的も勘案し判断することになります。例えば、定年前に部長職に対する役職手当として10万円支給されていたものが、定年後は役職が解かれ不支給となった場合は、同一労働同一賃金上の違法性は無いものと考えられますが、定年後も部長職(もしくは同様の職務)を継続し、何ら勤務内容に変更が無いにも関わらず、役職手当がカットされた場合、違法となる可能性があります。 定年再雇用後の賃金は、「職務内容」と「職務内容および配置の変更範囲」およびその他の事情に照らし、合理性のある金額とする必要がありますので、一律に定年前賃金の●%等と決定されないよう、お気をつけ下さい。 賃金・労働条件の設計こそ、専門家(社労士)に 以上のように、同一労働同一賃金を考慮した定年後再雇用者の賃金設計は容易ではありません。違法とならないよう設計するためには、下記手順を踏むなど、合理的な対応が必要となります。 ① 各待遇の性質や支給目的を明確にする ② 正社員への付与状況を洗い出す ③ 短時間・有期雇用者への付与状況を洗い出す ④ 上記②③に違いがある場合、その理由を洗い出す ⑤ 上記④の理由が、「職務内容」と「職務内容および配置の変更範囲」によるものでない場合、その差を是正する。 理由が、「職務内容」と「職務内容および配置の変更範囲」等によるものであっても、その違いに応じた差とする。 上記のようなステップを踏んでも、結局「この金額でいいのだろうか」と判断に悩まれる方が多いと思います。そのような場合は、専門化である弁護士や社労士へ相談されることをお勧めします。
-
就業規則の賃金規程例と変更の際の注意点を解説
就業規則における賃金規程とは 企業が従業員を雇用する上で重要となるのが「就業規則」です。とりわけ従業員の関心が高いのが「賃金規程」ではないでしょうか。本記事では、賃金規程の概要と作成・変更のポイントをご紹介します。給与規程と賃金規程の違い 賃金規程とは、従業員の給与や手当など、企業が支払う賃金の内容や計算方法を定めた規程のことです。就業規則の一部に盛り込まれているケースや「給与規程」という名称で別に定める企業もあります。 なお一般的に「賃金規程」と「給与規程」はほぼ同義で使われ、呼び名によって法的差異があるわけではなく、重要なのは労働基準法などの関連法規に沿って、必要な事項を明確に定めているかという点です。賃金規程の作成に必要な事項 賃金規程を作成する際には、以下の項目を明確にしておくことが求められます。1. 賃金の決定 ・基本給や各種手当の決定基準、給与テーブルなどを明確にする2. 賃金の計算および支払いの方法 ・時間外労働や休日労働に対する割増賃金の計算方法 ・現金による直接払いか金融機関への振り込みか3. 賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項 ・支払いの期日(毎月〇日締、○日払い)のルールはどのようなルールか ・昇給はいつ、どのような方法で行うか4. その他支払いに関するルール ・賞与や退職金、通勤手当・住宅手当など各種手当について賃金規程は、従業員に直接影響する重要な規定です。漏れがないように、労働基準法や関連法規に基づいた記載が必要です。 給与計算で残業代を計算する際「残業の単価をどのように求めたらよいか分からない。」「遅刻や早退をした場合の控除の計算はどのようにしたらいいの?」といったお問合せを受けることがあります。この点、たとえ賃金規程に計算方法の記載がなくても、残業代の単価の求め方は労働基準法施行規則第19条第1項に明示されているのですが、法律に不慣れな方が条文の内容を確認するのは容易ではありません。一方、遅刻や早退をした場合の控除方法は法律に定めがないものの、そうであるからこそ、どのように計算したらよいか戸惑うことが多いのではないでしょうか。 毎月異なる給与計算方法では、従業員の不信感を招く恐れがあります。そこで法律を理解し、日頃から給与計算に精通している社会保険労務士と共に、実務において役立つ規程になるようしっかり賃金規程の整備を行いましょう。賃金規程の記載例 賃金規程を就業規則に盛り込む際には、以下のような形式で記載します。第〇節 総則 第○条(賃金の決定・計算方法) 1.賃金の計算期間は毎月1日~末日までとする 2.賃金は毎月末日を締切りとし、翌月〇日に支払う。支払日が休にあたる場合は支給日を変更することがある。 第〇節 基本給 第〇条(基本給) 案1)職務等級および勤務年数に応じて次の表に従い決定する。 案2)年齢、経験、能力、職務の困難度・責任の程度、勤務成績、勤務態度等を考慮して各人ごとに決定する。 第〇節 各種手当 第〇条(役職手当) 役職手当は次の通り毎月支給する。 部長:○○〇〇円 課長:○○〇〇円 係長:〇〇〇〇円 第〇条(通勤手当) 1ヶ月の通勤定期券代を上限に実費を支給する。 第〇条(時間外勤務手当) 時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金は、労働基準法の定める率により算出する。 【明確化のポイント】 ・基本給の計算方法 具体的な賃金テーブルがあればそれを明示する ・割増賃金の計算方法 時間外労働(残業)や休日労働、深夜労働など、それぞれ労働基準法で定める割増率(25%、35%、25%など)を乗じて算出する旨を記載する ・手当の計算方法 通勤手当は距離や交通手段による一定額、役職手当は役職に応じた固定額など、支給基準を明確化することが重要なお、基本給の項目に「基本給は個別の契約で定める。」のような記載がされている規定を見かけますが、賃金規程に定めるべき事項は「賃金の決定方法」に関する事項ですので、「個別の契約で定める」の記載では不十分と言えます。また欠勤や遅刻早退をした際に給与を減額支給したい場合には、どのような計算方法で減額するか、端数処理はどうするか、などについても明確にしておきましょう。別に定める場合の記載例 賃金規程に関連するものとして、賞与や退職金について賞与規程や退職金規程などを別途定める企業もあります。これらは「相対的必要記載事項」の項目とされ、企業で設ける場合にはそのルール(支給対象者、支給時期、支給方法、支給対象期間や支給要件等)を規則規程等で明示しなければならないとされています。賃金規程変更時の注意点 先に記載の通り、賃金規程を変更する場合、従業員に「不利益」となる内容が含まれるときは特に注意が必要です。労働契約法によると、就業規則の内容を不利益に変更する場合は、変更について合理性が求められますので(従業員が受ける不利益の程度、変更の必要性や内容の相当性、労働組合等との交渉状況、その他の事情等に合理性があるか)、従業員等と十分に協議し、納得を得るよう努めましょう。また企業の経営状況等やむを得ない理由による変更であっても、変更を正当化ができる理由があるかどうか、明確に示さなければなりません。確認すべき関連する法律 • 労働基準法 賃金の最低基準や割増率などが定められています。• 最低賃金法 地域別最低賃金を下回らない金額設定が必要です。• 労働契約法 労働契約の締結、変更、解雇および雇止めに関するルール等が定められています。• 男女雇用機会均等法・パートタイム・有期雇用労働法 従業員の雇用形態による不合理な格差を生じさせないように配慮が必要です。賃金規程変更に必要な手続き 賃金規程変更時語は、以下の手続きを踏むのが一般的です。1. 変更案の作成 変更内容を具体的な条文としてまとめる。2. 従業員への説明・意見聴取 従業員代表や従業員に対して説明会を実施し、従業員代表から意見を聴取する。必要な書類と記載事項 • 改訂後の賃金規程 新旧対照表等を作成し、どの部分がどのように変更されたかを明確にします。• 説明資料 従業員向けの説明会に使用する資料や、FAQなどを整備すると円滑に進めやすく なります。• 同意書・承諾書(必要に応じて) 不利益変更を伴う場合は、従業員の個別同意が必要となるケースもあるため、同意書等の書面を用意しておくのが良いでしょう。従業員代表意見書の提出 就業規則や賃金規程を変更する際には、労働基準法に基づき、従業員代表の意見を聴取した書面(意見書)を添付する必要があります。ただし、意見書はあくまで「意見」の提出であり、同意を得る義務が必ずしも発生するわけではありません。しかし、不利益変更の場合は実質的な同意の有無がのちに争点となることが多く、慎重に対応する必要があります。なお、意見徴収する際『どのような人にお願いをしたらよいですか?』との質問を受けることがあります。法律上は「労働組合や労働者の過半数代表者に意見を聴くこと」と記載されているのみで、実際はどうしたらよいか分からない方も多いようです。 この点、行政通達においては①管理監督者ではないこと ②使用者の意向によって選出された者ではないこと 以上2点のいずれも満たすものでなければならないとされています。特に注意すべきは②ではないでしょうか。お願いしやすい従業員に、ついお願いしてしまいたくなりますが、それでは法が求める意見聴取の要件を満たしていないことになりますので、ご注意下さい。労基署への届け出 常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則や賃金規程を作成・変更した場合に、労働基準監督署へ届け出る義務があります。届出を怠ると、行政指導や罰則の対象となる可能性がありますので注意しましょう。賃金規程の従業員への周知義務 就業規則や賃金規程は従業員にとって労働条件を確認するうえで不可欠なものです。労働基準法にもとづき、「常時各作業場の見やすい場所へ掲示する」または「社内ネットワークで閲覧可能にする」など、従業員がいつでも閲覧できる状態にする必要があります。周知義務を怠った場合も、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。賃金規程と実態があっていない場合のリスク 就業規則や賃金規程等と、実態が異なる場合、以下のようなリスクが考えられます。1. 未払い賃金等の請求 各種手当や割増賃金が規定どおり支払われていないと、後に従業員から請求される可能性があります。2. 行政による是正勧告や罰則 労働基準監督署の調査で違反が発覚した場合、是正勧告や罰則が科されることがあります。3. 労使トラブルや信用失墜 就業規則との不一致は従業員の不信感を招き、その結果トラブルの増加や離職の増加につながるおそれがあります。労務トラブルを未然に防ぐためにも、就業規則・賃金規程は定期的に見直し、最新の法令や社内実態に即した運用を行うことが重要です。社労士に依頼するメリット 賃金規程は、企業、従業員双方にとって大変重要な規定です。企業規模や業種・職種によって適切な内容は異なりますが、法律を遵守しながら、実態に合った形で定めることが求められます。特に変更時には従業員と十分な協議を行い、合理性と合意を得たうえで進めましょう。社会保険労務士などの専門家に相談することで、よりスムーズな運用とリスク回避が期待できます。 なお当事務所には企業の問題を未然に防ぐお手伝いをする社会保険労務士、問題が発生した場合にその解決を行う弁護士の双方が所属していますので、双方の視点に配慮した賃金規程の作成を行うことが可能です。貴社の就業規則や賃金規程の作成・変更でお困りの際は、ぜひ愛知総合法律事務所の社会保険労務士へご相談ください。
-
就業規則「解雇事由」の記載例を社労士が解説
就業規則に規定できる解雇とは 就業規則では解雇に関する事項は絶対的必要記載事項であり必ず記載が必要です。解雇には大きく普通解雇、懲戒解雇、整理解雇があり、就業規則にはそれぞれの解雇に該当するのはどのような場合かを規定します。法律上解雇が禁止されている事由 解雇には法律上禁止されているものがあります。具体的には以下の例が挙げられます。 ・労災による疾病や療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇 ・女性従業員の婚姻、妊娠、出産、産前産後休業等を理由とする解雇 ・従業員の国籍、信条又は社会的身分等を理由とする解雇 ・従業員が育児休業、介護休業等を取得したことを理由とする解雇 ・従業員が会社の各種法令違反を社内外に告発したことを理由とする解雇 解雇・退職・辞職の違い 従業員が職場を辞める理由は解雇・退職・辞職のいずれかであると思います。それぞれどのような意味合いをもつか解説します。解雇とは従業員が起こした問題行為を理由として会社側が一方的に労働契約を打ち切る処分のことをいいます。 退職とは従業員が自らの申出によって労働契約を終了させることをいいます。辞職とは退職と混同されてしまいがちですが、自らの意思で会社を辞めるという意味においては同じであるものの、一般の従業員ではなく主に役員が会社を辞める際に用いられます。 ここからは解雇の内容について詳しく解説します。普通解雇とは 普通解雇とは懲戒解雇や整理解雇以外の解雇のことで、いわゆる従業員の職務怠慢や能力不足、病気やケガによる就業不能などを理由とする解雇のことを指します。 就業規則には普通解雇に該当する事由を明記します。しかし就業規則に定める解雇事由に該当したとしても、必ずしも解雇が認められるとは限りません。行われた解雇が有効か否かを判断するには、解雇に至る経緯や状況など様々な点を確認し、その解雇に客観的に合理的な理由があるか、社会通念に照らしても相当な判断(必要性)であったかどうかが問われます。(労契法第16条)解雇までの流れや理由 普通解雇を行う際は以下のような流れで行います。① 解雇に至る経緯の確認(本人からの聴取含む)今回の解雇をどのように進めてゆくか、ある程度の方針を固めた上で、対象従業員および関係者から事情聴取します。② 解雇事由(理由)の検討上記①を踏まえ、従業員の行為が就業規則に定める解雇事由相当かを検討します。 この時、例えば勤怠不良や本人の能力の欠如が問題とされている場合は、その事実のみならず、これまでの指導歴や今後もその状況が継続する可能性があるかどうか、本人の情状および同様のケースにおける他の従業員に対する処分との均衡など、様々な事情を総合的かつ冷静に判断することが必要です。③ 対象者へ解雇予告検討の結果、解雇相当と判断した場合は、就業規則に定める解雇の手続きに沿って対応を進めます。多くの会社が法令に従い「30日前の解雇予告もしくは解雇予告手当の支払を行う」と定めていると思います。 解雇予告は口頭でも有効ですが、トラブル防止のために書面を作成し本人へ渡すのが安心です。 なお書面に記載する解雇理由は就業規則の記載内容と紐づくような記載を行いましょう。普通解雇について記載例 解雇予告年月日:令和〇年〇月〇日 解雇年月日 :令和〇年〇月〇日 解雇事由 :・・・・・・・・・・・・・・・・ 解雇理由 :就業規則第〇条に定める「勤務成績や能力が著しく不良で、 業務に適さないと認めたとき」に該当するため。病気による解雇・休職期間中の解雇について 多くの会社では私傷病により休職し、休職期間満了日までに復職できない場合は「休職期間満了日をもって自然退職」もしくは「休職期間満了日をもって解雇」などと就業規則に定められているのではないでしょうか(自然退職の場合、実務上は自己都合退職として処理されるのが一般的)。対象の従業員がでた場合は、自社の就業規則がどのような定めをしているか、あるいは何も定めていないかを確認の上、規則に沿った対応を行いましょう。なお会社は休職期間満了まで、定期的に従業員のけがや病気の状況を把握するよう努め、本格的な復帰の前には「リハビリ出勤」を試みるなど、従業員の不安解消や復帰しやすい環境作りを行うことも従業員の早期復帰に効果的です。ただ就業規則に定めがあり、規則通りの対応をしていても、当該退職や解雇について後に従業員から「不当な取り扱いだ」として、裁判等の大きな問題にまで発展する場合もあります。この様なリスクを回避するためにも、就業規則に定めた休職手順や休職期間は適切か(例えば、休職期間が不当に短すぎることはないか、復帰の判断は適切であったか、休職満了時に従前業務はできないものの、他の業務は行えるということはないか、障害の特性に配慮したか等)適宜見直しを行いましょう。 懲戒解雇とは 懲戒解雇は懲戒処分の中で最も重たい処分であり、会社の秩序を大きく乱す違反や自身の重大な非行に対する“制裁”として行われる解雇の一つです。会社規定にもよりますが、懲戒処分は退職金等が支払われないケースが多く、支払われたとしても大きく減額されるなど従業員にとって大変厳しい処分と考えられます。先に記載の通り、解雇が有効と認められるためには客観的合理性と社会通念上の相当性が必要ですが、懲戒解雇の場合も同様です(労契法第15条・16条)。懲戒解雇が有効となるために具体的には以下のイ~二の要件を満たす必要があることから、懲戒解雇を行うには就業規則への懲戒事由の規定は必須であると言えます。イ) 懲戒事由や懲戒の種類が明記された就業規則があり、周知されていること ロ) 就業規則に定めた規定が合理的な内容であること ハ) 処分されるべき行為が就業規則に定める懲戒事由に該当すること ニ) その他の要件 主な懲戒解雇事由と記載例 懲戒解雇と認められる主な事由には以下が挙げられます。 ・重大な業務命令違反 ・業務上横領 ・業務上知り得た機密事項の漏洩 ・他の従業員に対する暴行 ・強迫 ・名誉毀損 ・会社の名誉や信用を著しく毀損し、会社に損害を与えたとき ・長期間にわたる無断欠席 など 上記を就業規則に明記する場合の規定例は以下の通りです。懲戒処分の種類(懲戒解雇であること)、合理的な懲戒事由を明記しましょう。【規定例】 第〇条(懲戒解雇事由) 従業員が次のいずれか一つに該当する場合は、懲戒解雇に処する。ただし情状によっては、諭旨解雇、減給および降格にとどめることがある。 ① 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令等に従わないとき ② 他の従業員の就業環境を著しく害するようなハラスメント行為・強迫・名誉棄損を行ったとき ③ 業務上知り得た会社の重要な情報を漏洩し、会社に損害を与えたとき ④ 正当な理由なく無断欠勤が〇日以上に及び、出勤に応じないとき : ⑩ その他全各号に準ずる行為が認められたとき懲戒解雇事由と諭旨解雇の違い 諭旨解雇は従業員が懲戒解雇に相当する違反をした場合に、会社が従業員に退職を勧告し、退職届の提出を促した上で解雇するもので、懲戒解雇に次ぐ重たい懲戒処分です。 懲戒解雇に相当するような事案であっても、従業員に情状酌量の余地がある場合や本人が深く反省している場合には諭旨解雇となる傾向がみられます。 また退職金の支給がほとんどされない懲戒解雇と違い、諭旨解雇の場合は退職金が支給されることが多い印象です。(個々の会社の就業規則により異なります。)整理解雇とは 整理解雇は会社が人員削減を目的として行う解雇で、主に経営不振や業績悪化が原因とされます。整理解雇も解雇の一つですが従業員に落ち度はなく、会社側の事情による解雇であるという点で、普通解雇や懲戒解雇と異なります。 昨今、新型コロナウイルスの影響により整理解雇を迫られる会社も多くあると思います。しかしたとえ経営不振が理由であったとしても、会社は従業員を簡単に解雇できるわけではなく、他の解雇同様その整理解雇の客観的合理性や社会通念上の相当性が問われます。 なお整理解雇が有効となるために具体的には以下イ~二の要件を満たすことが必要です。就業規則への規定は必須でないものの、例えば解雇回避のために他社への出向や転籍を行う場合には、その根拠が就業規則に定められているのが望ましいでしょう。イ) 人員削除の必要性があること ロ) 解雇を回避努力や経費削減等を講じたこと ハ) 解雇対象者の選定に合理性があること ニ) 解雇対象者や労働組合に十分な説明を行い、誠実に協議を行ったこと 整理解雇事由の記載例 整理解雇について就業規則に定める場合は(普通)解雇事由の条項に以下のような文言を記載しておくのがよいでしょう。【規定例】 ・会社はやむを得ない事業上の都合により従業員を解雇することがある ・会社は事業の縮小などにより、人員の整理による解雇を行う場合がある など 第〇条(出向) 会社は、業務上の必要性がある場合、関係会社や他社への出向を命ずる場合がある。なお従業員は正当な理由がない限りこの命令を拒むことはできない。 解雇予告とは 従業員を解雇する際は、法律上対象者に事前予告しなければなりません。この予告は解雇の少なくとも30日前までに行う必要があります。(労基法第20条、第119条)なお解雇日までに30日以上の日数がない場合は、解雇予告をした上で30日に不足する分の解雇予告手当を支払わなければならず、また即日解雇を行いたい場合は30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。解雇予告は取扱いが複雑なため、これら法律のルールを就業規則に明記している会社が多い印象です。解雇予告手当の計算方法 解雇予告手当の額は平均賃金に30日分、もしくは予告期間が30日に満たない場合はその日数分を乗じた額となります。なお平均賃金とは「算定すべき事由の発生日(解雇日)以前3ヵ月に対象者に支払われた賃金の総額」を「その期間の総日数(暦日数)」で除した金額をいいます。臨時に支払われる賃金や3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)は含まれません。また賃金締切日がある場合は、その起算日は直前の賃金締切日を用いること、賃金が時間額や日額、出来高払の場合は、最低保障額があることなど、その他にも細かいルールがあります。計算を行う際は事前に専門家である社労士に相談するのがお勧めです。就業規則がない場合の解雇はどうなる? 就業規則を作成していなければ「懲戒解雇」を行うことができません。 懲戒解雇を行うには就業規則に予め具体的な懲戒解雇事由を定めた上で、その就業規則の周知が必要と考えられているからです。 懲戒解雇をはじめとする懲戒処分は、社内の規律維持にとても重要な役割を担います。従業員の問題行為に処分を下せなければ社内秩序が乱れ、従業員間のトラブルが増加する、会社が従業員を制御することが難しくなるなど、様々な問題が発生するリスクがあります。 一方、就業規則に記載があれば従業員の非違行為への抑止力になり、実際に懲戒解雇を行う場面では、明確な懲戒解雇の根拠を示すことが可能になる等の効果が期待できます。もっとも懲戒解雇事由は労働基準法に定める就業規則の絶対的必要記載事項の一つですので、必ずその根拠事由の記載が必要です。就業規則作成を社労士に依頼するメリット 解雇を行うには就業規則への解雇事由の記載が不可欠です。しかしいつ起こるとも知れない解雇に備え予め就業規則を整備することは容易ではありません。そこで就業規則の作成にお悩みの際は、社会保険労務士へご相談頂くのがお勧めです。 また 愛知総合法律事務所には社会保険労務士だけでなく、弁護士、司法書士、税理士も在籍しており、解雇のみならず今後発生が見込まれるトラブルを想定した上でのご提案が可能です。まずはお気軽にご相談ください。就業規則作成・変更に関して無料でご相談を受けております。詳しくはこちら。






