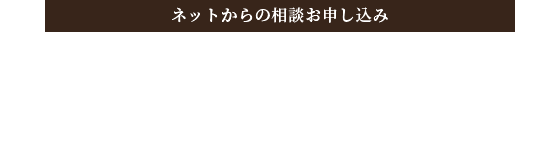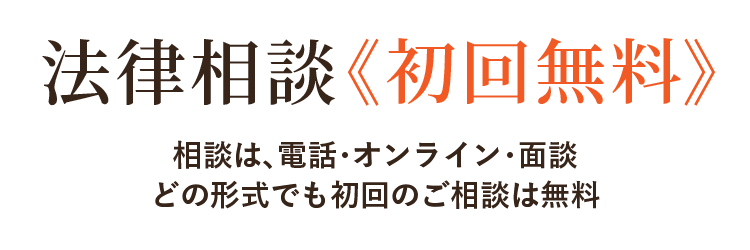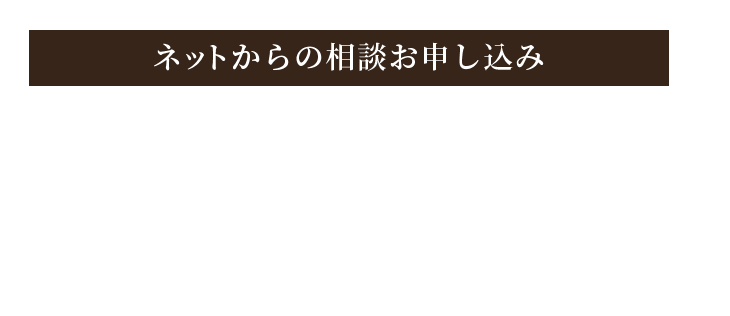本事務所のホームページをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。
弁護士法人愛知総合法律事務所大阪心斎橋事務所所長の弁護士居石 孝男です。
皆様の中には、突然、交通事故、離婚、相続、企業法務問題、消費者被害、犯罪などの様々な法律トラブルに巻き込まれてしまい、どのように対応すればよいのか分からず、不安を抱えている方がいらっしゃるかもしれません。
私は、弁護士として、そのような方々の不安に寄り添いながら、真剣誠実に問題に向き合い、相談者・依頼者の方々にとって最適な解決を図ることができるよう職務に臨んでいきたいと思っています。
大阪心斎橋事務所は、大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅、大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅より徒歩すぐに立地しております。
大阪市内の方はもちろんのこと、近隣市、府県の方々もアクセスのしやすい場所に事務所を構えており、面談対応、WEB・電話対応などお気軽に弁護士にご相談を頂けるような体制を所員一同整えております。
「こんなことを弁護士に相談してもよいのだろうか。」などといったことはお気になさらず、どんな些細なことであっても、どうぞお気軽にご相談ください。